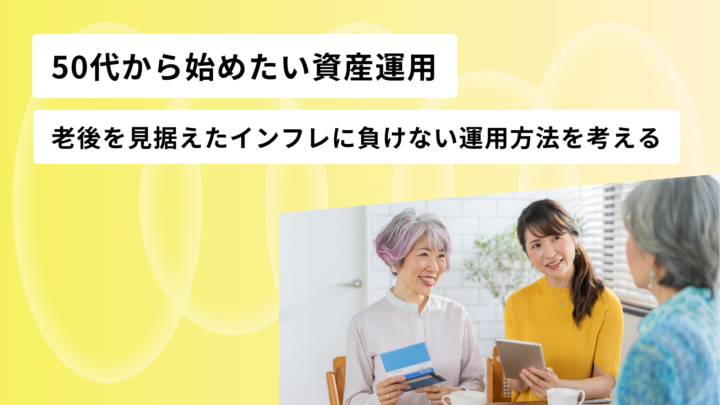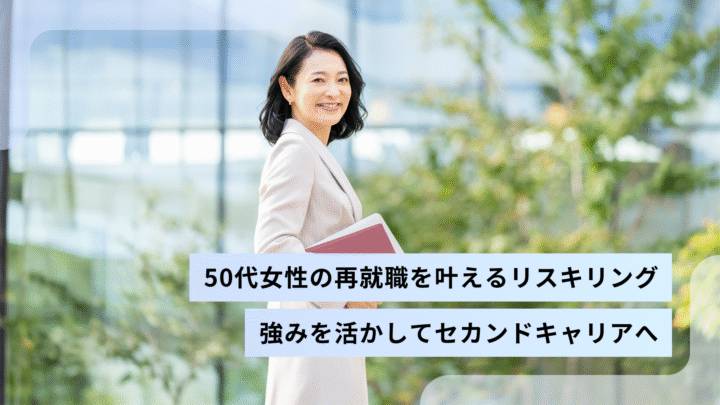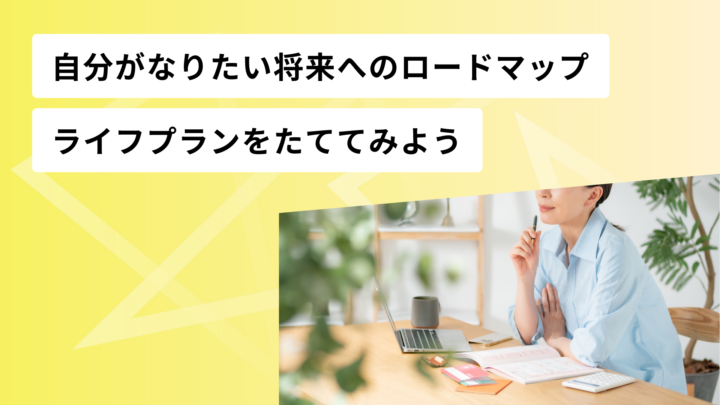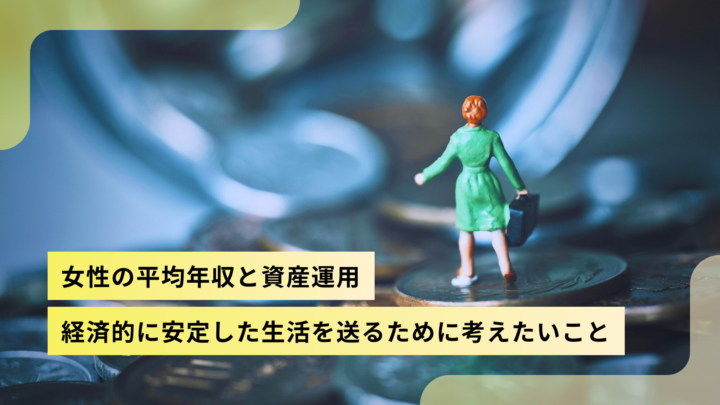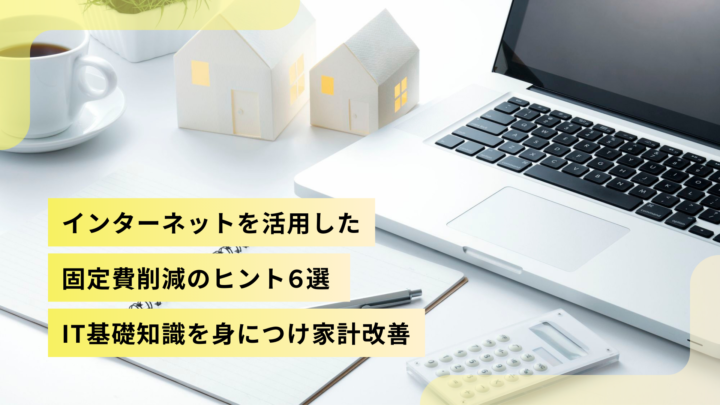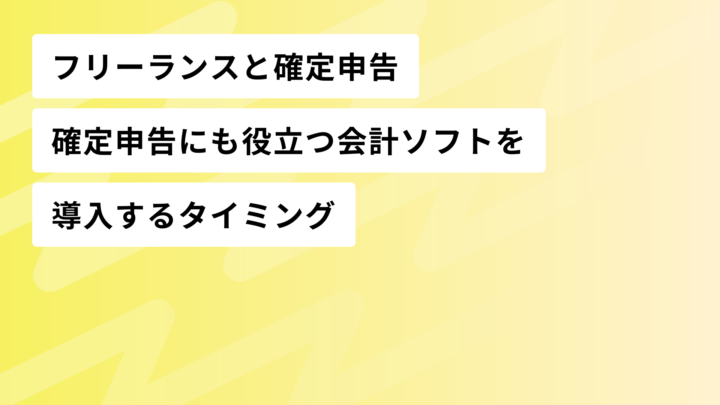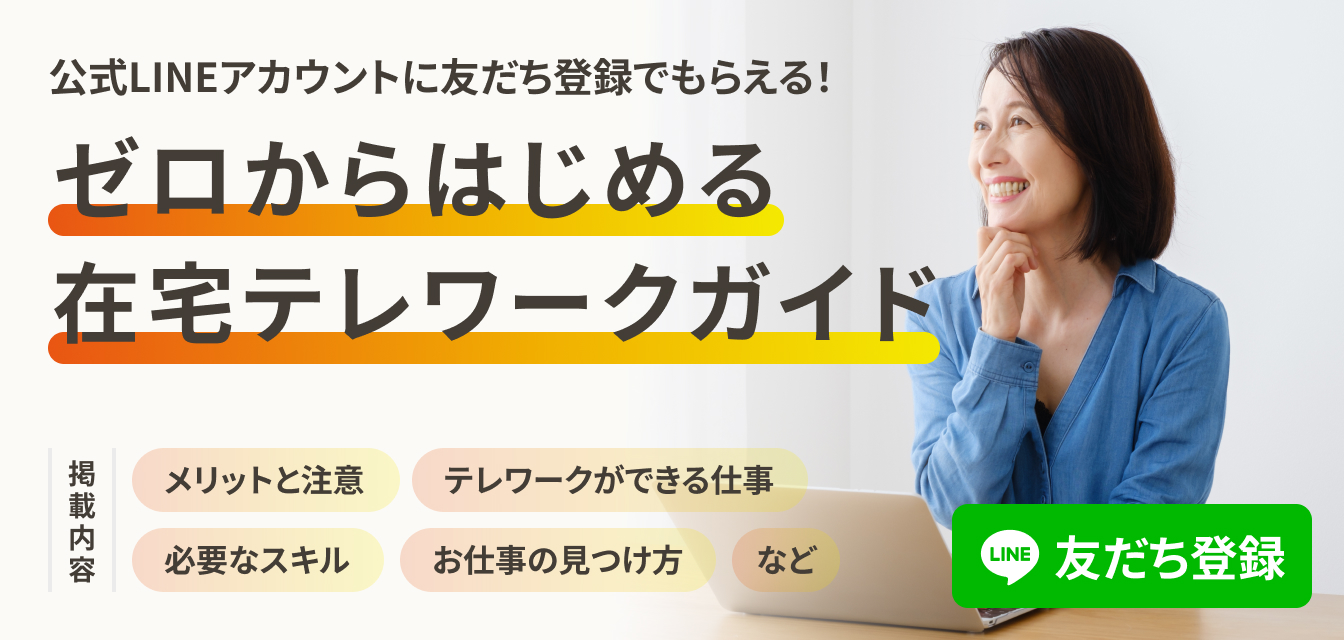-1440x810.png)
【50代女性】平均年収はいくら? 業種・地域・雇用形態から年収アップのヒントを解説
物価の上昇が続くなか、「自分の年収が他の50代女性と比べて高いのか低いのか?」と気になる方も多いのではないでしょうか。とくに50代は老後に向けた資金づくりや、住宅ローンの完済時期が近づくなど、将来の家計への関心が高まる時期でもあります。
そこで本記事では、国税庁や厚生労働省の最新データをもとに、50代女性の平均年収や、業種・地域・雇用形態による年収の違いを詳しく解説。さらに「どうすれば年収をアップできるのか?」という具体的なヒントや、リスキリングによるキャリアの伸ばし方についても取り上げます。ぜひ今後の人生設計にお役立てください。
目次
【2025年版】最新の調査で見る50代女性の年収データ
まずは、国税庁のデータなどを参考に、50代女性の平均年収がどれくらいか、年齢による年収の推移などを見ていきましょう。そして、これから必要となる将来への経済的な備えについて考えてみましょう。
50代女性の平均年収は300万円台前半 男女差から見る年齢による年収の推移

国税庁「民間給与実態統計調査」(令和5年)によると、50~54歳女性の平均年収は343万円、55~59歳女性では330万円という結果が出ています。一方、同年代の男性は50~54歳で689万円、55~59歳では712万円。男性と比べて、女性の平均年収が半分ほどになっていることがわかります。
また、男性は10代から50代まで、平均年収が着実に上昇しているのに対し、女性は20代後半から50代まで大きく年収が伸びないという傾向が。ここには、結婚・出産・育児・介護といったライフイベントで働き方を変えざるを得ない現実が大きく影響していると考えられます。
女性の正規雇用率の低さも年収に大きく影響
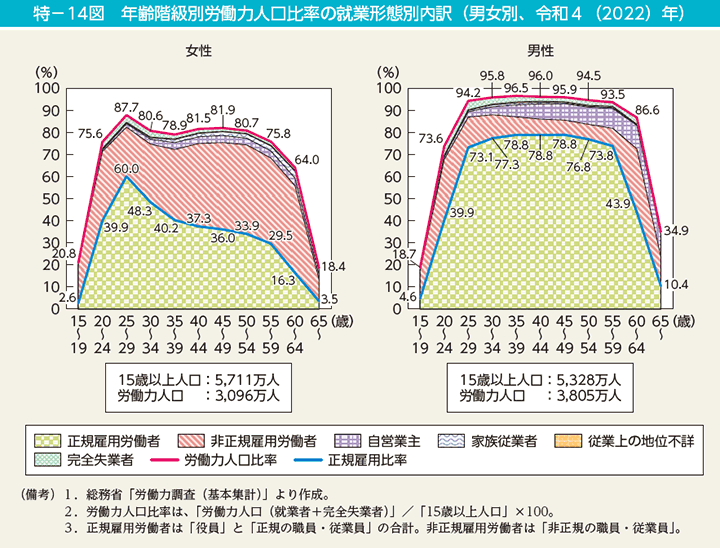
出典:内閣府『男女共同参画白書 令和5年版』
内閣府『男女共同参画白書 令和5年版』によれば、男性は20代から50代まで正規雇用率が70%台を維持しているのに対し、女性は25~29歳での60.0%がピーク。その後30代から50代にかけて結婚・出産・育児などのライフイベントを機に、右肩下がりで正規雇用から離れる傾向が見られます。
非正規雇用の割合が高まるほど、平均年収は上がりづらくなるため、介護や自身の健康問題も起こりがちな50代以降はさらに年収水準が低くなりがちです。
貯蓄などの資産はどのくらい? 老後を見据えた年収の見直しが必要
50代といえば、老後を見据える時期。老後の備えとして、現在の貯蓄などの資産と今後の資産形成を考慮にいれつつ現在の年収を見直したとき、将来の家計が成り立つのか、理想的なライフスタイルを保てるか、などを考える必要がでてくるでしょう。
「家計の金融行動に関する世論調査」(令和6年)によると、単身世帯でも二人以上世帯でも、「十分な金融資産がないから」が一番多い心配事、次いで「年金や保険が十分ではないから」があがっています。
](http://we.maia.co.jp/wp-content/uploads/家計の金融行動に関する世論調査【二人以上世帯調査】より.png)
出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」[二人以上世帯調査](令和6年)
どれくらいの貯蓄があるか?金融資産があるか?について、同調査の「二人以上世帯調査」では、預貯金については平均362万円、保険や有価証券を含めた金融資産は平均989万円という調査結果です。
ただし、同調査では「平均値」は、少数の高額資産を保有する世帯によって引き上げられる可能性があるため、「中央値を用いて一般的な家計像を捉えることとする」とされています。
このため同調査の中央値でいえば、一般的な世帯で約350万円の金融資産がある、ということになります。
](http://we.maia.co.jp/wp-content/uploads/「家計の金融行動に関する世論調査」[二人以上世帯調査]より金融資産の保有額グラフ.png)
出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」[二人以上世帯調査](令和6年)
この調査結果によると、老後2000万円問題のことを考えれば、多くの世帯で老後の資金は不足している傾向にあるといえます。
50代女性は自分の収入を見直し、今後の人生を考えた資産形成、金銭的な計画をしっかり立て、実行に移していくステージにいることを意識する必要があります。
年収の高い仕事とは? 業種別にみる年収の違い

自分の年収は、自分の働きに見合っているか?ほかの仕事とくらべてどうなのか?など、業種別、地域別、雇用形態などによる年収の違いを見てみましょう。
国税庁の「民間給与実態統計調査」(令和5年)によると、年収が高い業種の上位は以下の通りです。(平均給与には、平均賞与、平均給料・手当を含む)
- 電気・ガス・熱供給・水道業 775万円
- 金融業・保険業 652万円
- 情報通信業 649万円

また、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和6年)の産業別データにおいても、「情報通信業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「金融業,保険業」「学術研究,専門・技術サービス業」が平均月間所定内給与額の高い上位にランクインしています。
ただし、「金融業・保険業」や「製造業」「建設業」では、女性と男性の間に大きな賃金格差があるという報告もあり、業界によっては女性の活躍度合いや役職の違いが、女性の平均年収に大きく影響していると考えられます。
都会は高く、地方は低い? 地域別の賃金格差
地域による賃金の差を考えてみたことはあるでしょうか。今はテレワーク、フルリモートでの就業など、地域をまたいで働ける時代。どれくらいの地域差があるのかチェックしてみましょう。
都道府県別の月収格差をチェック
「賃金構造基本統計調査」(令和5年)によれば、都心部ほど月収が高い傾向があります。調査では全国計で月収31万8300円となっていますが、それよりも年収の高い都道府県は、高い順に以下の通りです。
- 東京都:36.85万円/月
- 神奈川県:35.04万円/月
- 大阪府:34.0万円/月
- 栃木:32.3万円/月
- 愛知:32.18万円/月
一方、地方では月収が27万円~29万円前後。なかでも、月収が低い傾向にある地方では25万円前後と、最も高い東京との差が月10万円近く開くことがあります。
しかし、この賃金差が「生活の豊かさ」に直結するかといえば、そうでもないようです。
都会の賃金が高い理由と地方ならではのメリットとは
都市部は住居費や物価が高く、企業によっては「地域手当」などが給与に上乗せされることも、賃金を高めている一因です。
一方、地方では家賃や食料品など生活コストが安く、家計にやさしいメリットも。通勤圏内で都道府県をまたいで働ける場合や、テレワーク制度を活用できる会社なら、地方在住でも都市部の企業と契約することで比較的高い年収を得るチャンスもあります。
正社員と非正規 雇用形態による格差はどのくらい?
冒頭で紹介した内閣府の『男女共同参画白書 令和5年版』によると、50代前半の女性の正規雇用比率は33.9%、50代後半の女性では29.5%となっています。
では、正規雇用と非正規雇用では、どれくらい年収の差があるのでしょうか?
正社員かどうかで年収に大きな差が出る
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(令和5年)によると、50代女性が正社員・正職員として勤務している場合と非正規雇用の場合では、月収ベースで約10万円もの差があることがわかります。
- 50代女性で正社員・正職員の場合:月収約31万円
- 50代女性で非正規雇用の場合:月収約20万円
仮に年間で考えると、ボーナスや各種手当を加味してさらに大きな差が生じる可能性があります。
正社員転換や副業で収入を補う方法も
今後のことを考え、収入を増やしたい場合、非正規雇用から正社員への転換制度を設けている企業も増えているため、キャリアアップ制度や転職を視野に入れることで、年収アップを目指すことができるでしょう。
また、副業を許可する企業も近年増えているので、ライフスタイルに合わせスキルを活かせる副業で収入を補う選択肢もあります。
年収アップにつながる3つの方法

ここまで50代女性の平均年収、業種別、地域別、雇用形態などによる年収の違いなどを見てきました。
これから先、年収を上げるための働き方を考えた際に、どのように働き方を変えればよいのか、転職や副業を考える必要はあるのか……悩むこともありますよね。
ここでは年収を上げるために有効な方法として、「昇給・資格取得」、「転職・起業」、「副業」をとりあげます。
(1) 昇給・資格取得
国税庁の「民間給与実態統計調査」も示すとおり、日本では勤続年数が長くなるにつれ、男女ともに年収は右肩上がりとなる傾向があります。
資格取得や業務成績によって昇給する制度がある会社であれば、順当に給与アップを見込めることも。企業主導の講座やリスキリングなど、スキルアップに取り組める環境が整っているのであれば、ぜひ積極的に受講、活用してみましょう。
(2) 転職・起業
「50代からの転職は難しい」と言われてきましたが、年齢制限の禁止が法的に明確化されたことや、企業の人手不足などにより、近年では35歳を超えても転職が可能になってきています。管理職経験や専門スキルを活かせる業界への転職、あるいは起業という形で新たなチャレンジをする選択肢もあります。
転職エージェントは無料でサービスが利用できるうえ、自己分析や業界の情報提供、面接対策などのサポートが受けられる場合が多いので、ぜひ活用してみてください。
(3) 副業で新しい可能性を探る
就業規則の改定によって、副業OKとする企業が増えています。クラウドソーシングやオンラインサービスを利用することで、ライティング、プログラミング、Webデザイン、カウンセリングなど、自分の得意分野を生かした副業が可能でしょう。
小規模で副業を始めることには、リスクを最小限に抑えつつ、新しい働き方や収入源を開拓できるメリットがあります。
ITスキルを取得して年収アップ
年収を高めるためには、スキルを取得し自分の市場価値を高めることも有効でしょう。ここではIT系のスキル取得について見てみましょう。
リスキリングの重要性
デジタルトランスフォーメーション(DX)が進む現代では、ITスキルを磨くことが年収アップへの大きなカギになるといえます。特に「情報通信業」は平均年収が高い業種として挙げられており、プログラミングやデータ分析、Web関連のスキルを習得できれば、転職や副業で優位に立ちやすくなります。
リスキリングには補助金の活用も
IT人材の不足は、今後の日本にとって大きな問題のひとつといえます。このため、国主導でリスキリング(学び直し)への支援が行われています。
具体的には
- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(経済産業省)
- 人材開発支援助成金(厚生労働省)
などがあり、どちらも企業や企業を通した個人が補助金を受けることができます。このほか、教育訓練給付制度対象のITスキルを身につけるための講座もあります。
いずれも給付条件や給付対象をよく確認したうえでの申請が必要です。
在宅ワーク・テレワークの選択肢
ITスキルがあれば、テレワークの仕事も多く、場所にしばられずに働きやすくなるのも魅力のひとつです。例えば、親の介護や家庭の事情でフルタイム勤務が難しい場合でも、在宅ワークやフリーランスといった柔軟な働き方が選びやすくなります。
ライフシミュレーションで将来設計を見直そう
50代になると、「老後は何歳まで働くか」「住宅ローンをいつまでに完済するか」など、具体的な将来設計を考える必要性が高まってきます。
将来について考えるときには、年収アップだけでなく、支出や貯蓄額、健康状態など総合的にバランスを取ることが大切。このためには、ライフシミュレーションサイトを利用したり、生活スタイルを見直し長く働ける環境を整えることなどがバランスよく将来設計を立てるコツといえるでしょう。
- ライフシミュレーションサイトの活用
自分の収支や将来予測を数値化することで、現在の働き方を変えるべきかどうか判断しやすくなります。個人情報の取り扱いには十分注意のうえ、まずはシミュレーションでざっくりと把握してみましょう。 - 無理なく長く働ける環境を整える
体力面・メンタル面の不安がある場合は、雇用形態を変えたり、週3~4日の短時間勤務を選択するなど方法はいろいろあります。必要以上に背伸びをせず、自分に合った働き方を模索することが大切です。
まとめ:50代からでも遅くない! キャリアと年収を見直そう

人生100年時代と呼ばれるいま、50代はまだまだ折り返し地点。これまでの経験やスキルを武器に、年収アップを目指すことも十分に可能です。
- 業種・地域・雇用形態による違いを知り、自分が働く環境を再点検する。
- 昇給・転職・副業など、自分に合った方法で収入源を増やす。
- ITスキルや資格取得でキャリアの幅を広げ、在宅ワークやフリーランスの道も検討する。
- ライフシミュレーションで収支や将来の働き方を具体的に考える。
自分の市場価値や適正年収を知り、無理なく長く働ける環境を整えれば、50代からの人生をより豊かに変えることができます。焦らず少しずつ、今できることから始めてみましょう。
50代女性の年収についてよくある疑問(FAQ)
Q1:50代で未経験の業界へ転職するのは難しいですか?
A1: 近年は雇用対策法の改正などで年齢制限が緩和されており、人手不足の企業も多いです。未経験でも意欲や学習姿勢を示しやすい資格や研修制度を活用することで、チャンスが広がるでしょう。
Q2:副業でどのような仕事が人気ですか?
A2: オンラインで完結できるライティング、Webデザイン、プログラミングや、英語が得意な方は翻訳などが人気です。こういったスキルを身につけるには定額でさまざまなスキルを学び放題の「でじたる女子+」もおすすめです。(でじたる女子+はリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業に採択されています)
Q3:非正規雇用から正社員になるために必要なことは?
A3: ITスキルや資格取得のほか、コミュニケーション能力やマネジメントスキルを身につけると転職市場で有利になります。まずは社内で正社員登用制度を確認したり、転職エージェントのサポートを受けるのがおすすめです。
参考資料・出典
- 国税庁「民間給与実態統計調査」(令和5年)
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和5年)、(令和6年)
- 内閣府『男女共同参画白書 令和5年版』
- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」(令和6年)
50代からのキャリア戦略に迷ったら、まずは情報を集め、現状を客観的に分析することから始めてみましょう。家計を安定させつつ、自分の可能性を広げる働き方を見つけて、より充実した人生を築いていきましょう。